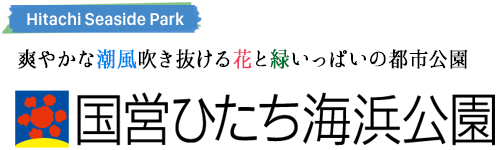みはらしの丘でコキアが『生育中(30cm)』となっております。


 (7月10日撮影)
(7月10日撮影)
今年は約40,000本を植栽しています。
◆
コキアとは、ヒユ科(旧アカザ科)ホウキギ属の一年草で、原産地はアジアです。
また、日本には中国から渡来したのではないかと言われています。
秋には真っ赤に紅葉する事で人気があります。
和名を「ほうき草」といい、昔はこの茎を乾燥させてほうきを作っていました。
実は「とんぶり」とも呼ばれ食用になります。
形や色、歯触りがキャビアに似ていることから「畑のキャビア」とも呼ばれ秋田県の名産となっています。
*当公園のコキアは観賞用となります。
◆
◆コキアを見学のお客様は『西口・翼のゲート』が便利です◆
ひなの林ではアジサイ “アナベル”が『見頃(後半)』です。



他のアジサイも見頃(後半)となっています。

 (7月10日撮影)
(7月10日撮影)
ひなの林でアジサイをお楽しみいただけます。
アジサイ ‘アナベル’ は北米原産のアメリカノリノキを改良して作出された品種です。
純白の小さな装飾花が密に集まった集合花は大きく、株一面に咲きます。
見ごたえがある独特の雰囲気を持った花と強健で育てやすい性質を備えており、日本でも大変人気があります。
◆
アジサイとは、アジサイ科アジサイ属に含まれる多くの植物の総称です。
日本から渡ったアジサイが西洋で盛んに改良され、今日では色鮮やかな品種が世界中で親しまれています。
国内では海外から逆輸入された品種を西洋アジサイ(ハイドランジアとも)と呼んでおり、日本においても一般的に流通しているものはこの仲間であることが多いです。
属名 Hydrangea はギリシャ語の hydro(水)と angeion(容器)から成り、水を多く吸い上げる性質や蒴果の形から名付けられたとされています。
◆
◆アジサイ ‘アナベル’ を見学のお客様は『西口・翼のゲート』が便利です。◆
スカシユリが咲いています。


 (7月10日撮影)
(7月10日撮影)
砂丘エリアでスカシユリをご覧いただけます。
一際色鮮やかなオレンジ色のこのユリは、今年も風雨に耐えながらきれいに花を咲かせています。
砂丘エリアは、公園ボランティアの「野生植物パートナー」がスカシユリの球根増殖・植付などを行っています。
是非砂丘エリアにも足を運んでいただければ幸いです。
◆
スカシユリとは、ユリ科ユリ属の多年草で海岸の砂地に自生しています。
名前の由来は、花弁の根元が細くなって隙間が出来、先が透けて見えることに因みます。
梅雨時期に咲き始めますが、雨がこの隙間から落ち、水がたまらない機能的な構造をしています。
◆
◆スカシユリを見学のお客様は『海浜口・風のゲート』が便利です。◆
ヤマユリが咲いています。


 (7月10日撮影)
(7月10日撮影)
記念の森の散策路でヤマユリをお楽しみいただけます。
数は少ないですが、ユリの香りが一面に漂っており、とても存在感があります。
記念の森は公園ボランティア「記念の森パートナーズ」の方々が管理しています。
木漏れ日が揺れる森の中を散策してみてはいかがでしょうか。
◆
ヤマユリとは、ユリ科ユリ属で日本原産の多年草です。
東日本を中心とした本州に分布し、日陰がちの斜面や明るい林、草原に見られます。
また、球根は食べることもできます。
*本公園のヤマユリは観賞用です。
◆
◆ヤマユリを見学のお客様は『西口・翼のゲート』が便利です。◆
テラスハウス前花畑でヒマワリ”アポロン”が咲いています。



(7月10日撮影)
サイクリングをしながらご覧いただけます。
◆
ヒマワリは、キク科ヒマワリ属の一年草で原産地はアメリカです。
英名は「サンフラワー」、和名では「向日葵(ひまわり)」「日輪草(にちりんそう)」「日車(ひぐるま)」などがあり、どの名前も太陽に由来します。
”アポロン”という品種は、太陽神「アポロン」にちなんで名づけられました。
一般的なヒマワリよりも小ぶりな花を次々と咲かせます。
◆
◆ヒマワリ”アポロン”を見学のお客様は『西ゲート』が便利です。◆
グラスハウスでサンパチェンスが「咲き始め」となっています。

 (7月10日撮影)
(7月10日撮影)
グラスハウスでサンパチェンスが咲いています。
海と空、太陽の光を燦燦にあびているサンパチェンスといったここでしかみられない夏の風景をお楽しみください。
◆
サンパチェンスとは、インパチェンス属の種間雑種として、サカタのタネが開発したオリジナル品種です。
※インパチェンスとは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草です。
品種名の由来でもある“サン(Sun)=太陽 + ペイシェンス(Patience)=忍耐”という特性により、
暑さや強い日差しにも耐え、過酷な日本の夏でもたくさんの花を次々と咲かせます。
◆
◆サンパチェンスを見学のお客様は『海浜口・風のゲート』が便利です。◆